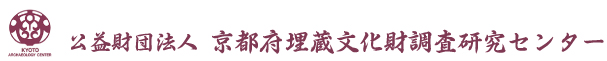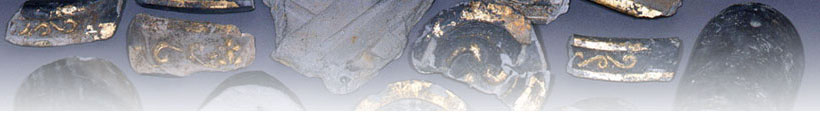|
平成23年度 発掘調査情報 |
|
| 遺跡名 | 長岡京跡右京第1023次・松田遺跡 |
| 所在地 | 乙訓郡大山崎町下植野一丁田 |
| 調査期間 | 2011/04/19~11/15 |
| 調査面積 | 850㎡ |
| 調査原因 | 道路建設 |
| 主な遺構 | 弥生:竪穴建物(竪穴式住居跡)
古墳:竪穴建物(竪穴式住居跡) 奈良末~ 平安初頭:掘立柱建物跡・溝・柵列 中世:井戸・土坑・溝 |
| 主な遺物 | 弥生:弥生土器
古墳:須恵器・土師器・フイゴ羽口・鍛冶滓 奈良末~平安初頭:土師器・須恵器・陶磁器・鉄器・鉄滓・フイゴ羽口 中世:土師器・須恵器・瓦器・中国製陶磁器 |
 |
| 調査地は大山崎中学校南側の大山崎町多目的広場に位置します。今回の調査では奈良から平安時代(長岡京に都があった頃)の掘立柱建物跡や柵列、区画溝、土坑、柱穴、自然流路のほか古墳時代の竪穴建物(竪穴式住居跡)、溝、弥生時代後期の竪穴建物(竪穴式住居跡)がみつかりました。 |
 |
| 掘立柱建物跡は6棟みつかりました。そのうち最も規模が大きい建物は東西3間(6.3m)×南北2間(5.4m)以上の建物で、柱穴は1辺約1mと大きなものでした。 |
 |
| 区画溝は幅約4m、深さ約30cmで、溝内に掘削された廃棄土坑から大量の土器が出土しました。高杯や皿類が多いことが注目されます。調査地周辺でも同時期の遺構が広範囲に分布すること、瓦が出土することから①長岡京がこの地域まで整備されていた、②長岡京期から平安時代の山崎津に関連する公的な施設があった、③平安時代に「長岡京南」に移された山城国府があった可能性が考えられます。 |
 |
| 古墳時代の竪穴建物(竪穴式住居跡)は2基みつかりました。そのうち1基の床面直上では炭化材が放射状に認められ、炭や焼土も分布することから焼失した住居であると考えられます。 |
 |
| 弥生時代の竪穴建物(竪穴式住居跡)は、平面形が八角形で総床面積が53.9㎡の大型住居です。中央には炉跡があり、壁際にはベット状遺構が5か所みつかりました。住居の北側には入り口と考えられる張り出し部があります。この住居も炭化材や炭や焼土が広がることから焼失したと考えられます。 |